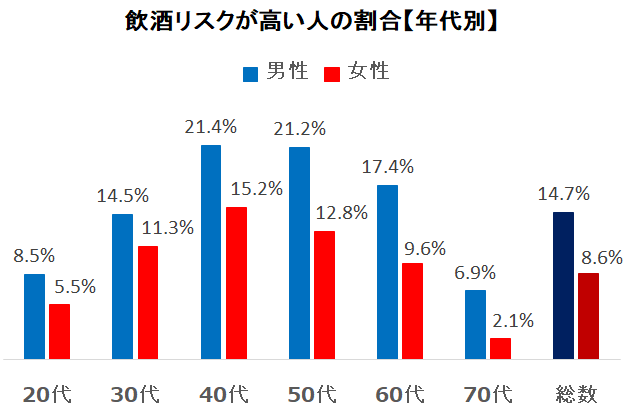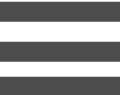毎日チューハイ2缶を飲む男性は、生活習慣病のリスクがある

国の調査で見る「飲酒」の現状
健康を維持するリスクとして「喫煙」が取り上げられることが多いのですが、「飲酒」も忘れてはいけません。
過度な飲酒は、生活習慣病のリスクを高める有害な存在です。
ここでは、厚労省の「国民健康・栄養調査」のデータをもとに、お酒のリスクについて見ていきます。
飲酒量のガイドライン
厚労省が「生活習慣病のリスクを高める量」としている、純アルコールの摂取量は、男性が40g以上、女性が20gです。
男性の場合、「週に5~6日、清酒を2合以上」飲むと、この水準を超えてしまいます。
女性は、この半分ですから「週に5~6日、清酒を1合以上」で該当します。
この量が、飲酒量のガイドラインになります。
チューハイ1缶は清酒1合に相当
「清酒1合」は、日本酒180mlのことです。
これを他の酒に換算すると、次のようになります。
- ビール/発泡週 中瓶1本(500ml)
- 焼酎 20度(135ml)
- 焼酎 30度(80ml)
- チューハイ 7度(350ml)
- ウイスキー ダブル1杯(60ml)
- ワイン 2杯(240ml)
つまり、缶チューハイの350ml缶を、男性なら毎日2本、女性なら毎日1本飲んでいれば、それだけで「生活習慣病のリスクを高める量」を超えてしまいます。
男性の「14.7%」、女性の「8.6%」が飲み過ぎ
「生活習慣病のリスクを高める量」を飲んでいる人は、どれぐらいの割合なのでしょう。
2017年の調査では、男性が「14.7%」、女性が「8.6%」です。
厚労省が関わっている健康維持活動の目標値は、男性が「13%」、女性が「6.4%」です。
しかし、過去数年分を見ても、男性は横ばい、女性はやや増加の傾向にあります。
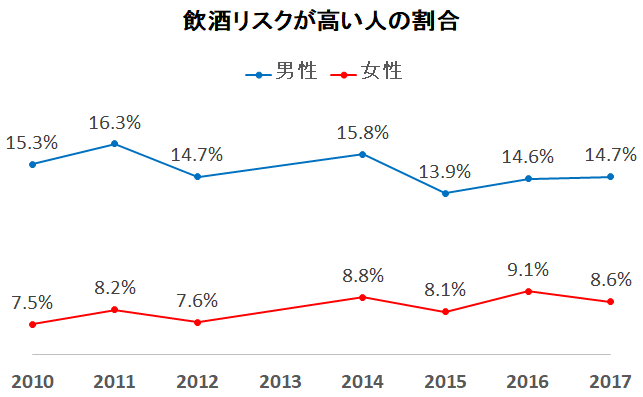
飲み過ぎが多い「40代」
「生活習慣病のリスクを高める量」を飲んでいる人を年齢別に見ると、男女とも「40代」が一番多くなっています。
飲酒量が多い人は、30代から増え始め、60代まで高い水準が続きます。
さすがに「70代以上」になると、酒量は減るようです。
生活習慣病は、すぐに発症するものではありません。40代前後に元気に飲んでいて、身体に自信を持っていても、あとで症状が出る可能性が高いのです。
自分の飲酒量を把握して、生活習慣病のリスクにならない量にコントロールしましょう。