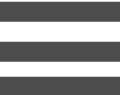7万円の給付金で注目されている「住民税非課税世帯」になる方法

7万円の給付で注目が集まる
世帯ごとに7万円の特別給付金が支給されるということで、「住民税非課税世帯」という言葉が注目を集めています。
この記事では、年金生活者が「住民税非課税世帯」になるための条件を中心に解説します。
「住民税非課税世帯」のメリット
「住民税非課税世帯」は、住民税が課税されないほど収入が少ない世帯のことです。
つまり、なにかあれば真っ先に支援の対象となるほど、生活が苦しい世帯と思えば良いでしょう。
今回のように支援金の対象となったり、健康保険料が安くなるなど多くのメリットがあります。
ただし、「住民税非課税世帯」になるには年収に一定の基準があります。
65歳以上に限っても「住民税非課税世帯」は3割しかいない
「住民税非課税世帯」になるのは簡単ではありません。
年金生活者が中心で収入が少ない「65歳以上」に限っても、「住民税非課税世帯」は34.6%しかいません。
それだけハードルが高いのです。
例えば、東京23区に住んでいる年金生活者の場合を見てみましょう。
年金以外の収入がないとすると、「住民税非課税世帯」になれる年金額は、単身者で「155万円以下」、扶養家族がいる場合で「211万円以下」になります。
この金額は公的年金等控除である110万円を引く前の金額ですから、かなり少ないと言えるでしょう。
月額にすると、単身者の場合で「13万円」、扶養家族がいる場合は扶養家族分も含めて「18万円」以上の年金をもらっていると、「住民税非課税世帯」になるのは難しいでしょう
いま、老齢年金の年額の目安は、次のようになっています。
- 国民年金(一人) 79万5,000円
- 厚生年金(夫婦二人分の目安) 269万3,784円
つまり、国民年金だけならば「住民税非課税世帯」になれる可能性がありますが、厚生年金の場合はなれない可能性が高いと思って良いでしょう。
地域によって収入の基準が変わる
「住民税非課税世帯」でやっかいなのは、住んでいる地域によって収入などの条件が異なることです。
例えば、同じ東京都であっても、地域の生活状況に応じて3つの段階があります。
さきほど例に挙げた23区では、扶養家族がいる場合の基準は「211万円以下」でしたが、羽村市などでは「201.9万円以下」、奥多摩町では「192.8万円以下」になります。
つまり、「夫婦二人の年金が211万円以下だから大丈夫」と、聞きかじりで判断すると危険です。
また、「住民税非課税世帯」になる条件は1つではありません。
例えば、生活保護世帯は無条件で「住民税非課税世帯」になりますし、障害者やひとり親の場合は条件が異なります。
自分が該当する可能性があるときは、必ず、もよりの市区町村の窓口に相談して確認してください。
年金を繰り上げ受給することで「住民税非課税世帯」になる
最後に、「住民税非課税世帯」になるための、ちょっと危険な方法についても触れておきましょう。
それは、自分の年金の金額が、微妙に「住民税非課税世帯」の基準を超えてしまうというときに使うテクニックです。
具体的には、65歳になる前に年金を繰り上げ受給することで、年金の金額、つまり年収を減らすのです。
しかし、「住民税非課税世帯」の基準は地域ごとに異なります。
また、制度も不変ではなく、何度も変わっています。
このテクニックを使うためには、減額する年金の金額について綿密な計算が必要です。
万が一にも、計算間違いは許されません。
しかも、苦労してクリアしても、引っ越しをしただけで「住民税非課税世帯」の条件が満たせなくなる可能性があります。
さらに、自分が生きている間に制度が変わって「住民税非課税世帯」から外れてしまう可能性もゼロではありません。
また、繰り上げ受給でいったん減った年金は生涯変わりません。
これからインフレになりそうな時期に、もともと少ない年金をあえて減額するのはリスクと言って良いでしょう。
つまり、このテクニックにはメリットもありますが、それなりのリスクもあることを承知の上で使ってください。