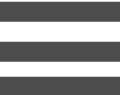ビールを一番飲むのは「札幌市」、ワインは「東京23区」

お酒の消費額
総務省統計局では、「家計調査」の一部として、お酒の消費額のランキングを公開しました。
これは、各地方を代表する都市に住む2人以上の世帯を対象に、お酒に使った金額を調べて、順位を付けたものです。
まず、お酒の種類順に10位までのランキングを見ていきましょう。
ビールをよく飲むのは「札幌市」
やはり、口開けは「ビール」から行きましょう。
1位は「札幌市」でした。
ビールの産地として知られる土地柄だけに、年間で「14,631円」も飲んでいます。
2位の「京都市」と、3位の「青森市」は、かなりの接戦で、1円差でした。
「京都市」はビールを飲む街というイメージが少ないのですが、数年前の調査では1位になっており、かなりのビール好きなのです。
- 札幌市 14,631円
- 京都市 14,064円
- 青森市 14,063円
- 大津市 13,671円
- 秋田市 13,572円
- 山口市 13,558円
- 新潟市 13,459円
- 盛岡市 13,166円
- 福井市 12,434円
- 松山市 12,241円
- 全国平均 10,906円
発泡酒は「高知市」
ビールに近い飲み物として「発泡酒」と、第三のビールとも呼ばれる「ビール風アルコール飲料」があります。
これらの消費量の1位は「高知市」でした。
2位の「新潟市」に、3,000円近い差を付けた、ぶっちぎりのトップです。
「新潟市」もお酒の消費量が多い街ですから、「高知市」の消費量の多さが分かります。
3位に「札幌市」が入り、ビール風のお酒全般をよく飲むことが分かります。
- 高知市 17,853円
- 新潟市 14,962円
- 札幌市 14,002円
- 山口市 12,390円
- 青森市 12,380円
- 富山市 12,095円
- 大阪市 11,804円
- 鳥取市 11,756円
- 秋田市 11,582円
- 宮崎市 11,189円
- 全国平均 9,045円
チューハイ、カクテルは「秋田県」
軽めのお酒として人気がある「チューハイ」や「カクテル」の1位は「秋田県」でした。
2位は「青森市」、3位は「山形市」で、いずれも東北地方の都市が入っています。
東北地方のお酒と言えば「清酒(日本酒)」のイメージが強いのですが、他のお酒も消費量が多いことが分かります。
- 秋田市 4,411円
- 青森市 4,064円
- 山形市 3,927円
- 高知市 3,763円
- 川崎市 3,751円
- 大阪市 3,730円
- 岡山市 3,705円
- 盛岡市 3,592円
- 神戸市 3,584円
- 宇都宮市 3,563円
- 全国平均 2,791円
焼酎は「宮崎市」
焼酎の1位は「宮崎市」でした。
全国平均の2倍以上の金額を飲んでおり、その勢いが分かります。
2位は「鹿児島市」、3位は「熊本市」と、九州地方の都市が入っています。
すごいのは4位の「青森市」で、焼酎の本場である九州勢に肉薄しています。
「青森市」は、ほとんどのお酒のランキングに顔を出しており、酒豪ぶりがうかがえます。
- 宮崎市 14,391円
- 鹿児島市 11,483円
- 熊本市 10,180円
- 青森市 10,161円
- 北九州市 9,625円
- 山口市 9,246円
- 広島市 8,965円
- 大分市 8,495円
- 山形市 7,605円
- 秋田市 7,594円
- 全国平均 6,417円

ウイスキーは「山形市」
ウイスキーの1位は「山形市」でした。
2位は「青森市」、3位は「札幌市」で、北の都市が上位を占めています。
- 山形市 3,127円
- 青森市 2,615円
- 札幌市 2,296円
- 仙台市 2,232円
- 秋田市 2,055円
- さいたま市 1,815円
- 新潟市 1,804円
- 千葉市 1,712円
- 松江市 1,711円
- 甲府市 1,705円
- 全国平均 1,627円
ワインは「東京都」
ワインの1位は「東京都区部」つまり東京23区が1位でした。
東京は、他のお酒のランキングには顔を出していませんが、「ワイン」でいきなり1位になっています。
そして、東京都区部は、全国平均の2倍以上のワインを飲んでいます。かなりのワイン好きと言えるでしょう。
2位は「横浜市」、3位は「川崎市」と首都圏の都市が続きます。
- 東京都区部 7,372円
- 横浜市 6,442円
- 川崎市 5,394円
- 福岡市 5,097円
- 千葉市 4,747円
- 甲府市 4,423円
- さいたま市 4,101円
- 松江市 4,075円
- 仙台市 3,991円
- 神戸市 3,957円
- 全国平均 3,319円
日本酒の1位は「秋田県」
清酒(日本酒)の1位は「秋田市」でした。
2位も「福島市」で、東北勢が続きます。
3位は「新潟市」で、4位の「富山市」とともに北陸勢が入りました。
他にも東北や北陸の都市が入っており、北の地方で強いお酒であることが分かります。
- 秋田市 10,253円
- 福島市 10,114円
- 新潟市 9,526円
- 富山市 8,464円
- 松江市 7,765円
- 盛岡市 7,703円
- 仙台市 7,507円
- 金沢市 7,426円
- 神戸市 7,149円
- 佐賀市 7,118円
- 全国平均 5,691円

他のお酒は東京都区部
ここまでの分類で出てこなかったお酒を「他の酒」として分類しています。
1位は「東京都区部」でした。
2位は「宇都宮市」、3位は「川崎市」と関東地方の都市が続きます。
- 東京都区部 1,622円
- 宇都宮市 1,290円
- 川崎市 1,253円
- 広島市 1,218円
- 富山市 1,203円
- 静岡市 1,202円
- 新潟市 1,165円
- 福島市 1,147円
- 盛岡市 1,136円
- 大津市 1,125円
- 全国平均 942円
総合ランキング1位は「新潟市」
すべてのお酒をひっくるめた総合ランキングの1位は「新潟市」でした。
「新潟市」は、「ビール」「発泡酒」「清酒」「他の酒」の4つのランキングに入っています。
2位は僅差で「青森市」でした。
「青森市」は、「ビール」「発泡酒」「チューハイ」「焼酎」「ウイスキー」と、新潟市よりも多い、5つのランキングに入っています。
しかし、「清酒」と「他の酒」でランキングに入らなかったのが影響して、500円の差で及びませんでした。
3位も僅差で「秋田市」が入りました。
「秋田市」は、「ワイン」との「他の酒」を除く6つのランキングに入っているのですが、わずかに及びませんでした。
- 新潟市 55,410円
- 青森市 54,907円
- 秋田市 54,798円
- 札幌市 49,953円
- 盛岡市 49,899円
- 山形市 49,613円
- 富山市 48,247円
- 山口市 47,364円
- 広島市 46,635円
- 高知市 46,506円
- 全国平均 40,738円