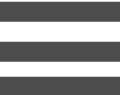厚労省の外郭団体が介護保険の計算ミスの内容を公開。自分が犯したミスの影響の大きさを知らず

ようやく分かったミスの実態
厚労省の外郭団体である「社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)」が、2019年1月に起きた介護保険料に関するミスについて内部調査の結果を公開しました。
このミスの詳細については、これまで公開された文書がありませんでした。
内部調査の結果をもとに、何が起きたのかを追ってみましょう。
1人当り2千円のミスが200億円の影響
今回、支払基金が誤ったのは「平成29年度被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担額」の金額です。
正しい金額は「65,489円」でしたが、これを計算するための保険者の数を間違ったために「63,433円」と、約2千円安く計算してしまったのです。
つまり、ミスの内容は、1つの数字でした。
誤った金額は、支払基金から厚労省に伝えられ、さらに健康保険組合などの医療保険を担っている団体へ伝えられました。
この誤った金額を使って、予算を編成してしまった医療保険の団体は次の3つです。
- 健保組合(最大1,380組合)
- 共済組合(最大85組合)
- 全国土木建築国保組合
これだけ規模が大きい団体が影響を受けたのですから、その影響もタダでは済みません。
1人当りでは約2千円の誤りですが、影響した総額は「201億円」におよびました。
つまり、医療保険の組合から支払基金へ払われる金額が、201億円足りないということになります。
実際には、支払基金は剰余金を持っていますので、足りない分は、そこから支出されます。つまり、支払基金が介護保険を運営している市区町村に払う分を建て替える形になります。
ですから、どこかの介護保険団体が予算不足になるようなことはありません。
しかし、誤った金額をもとにして予算を組んでしまった、3つの団体は、これから予算の修正や余剰金からの出費を余儀なくされることになります。
ミスは分かっても、その意味が分かっていない
ミスの内容もさておき、その後の対策の遅れは報告書からも、よく分かります。
主な流れを、時系列で見てみましょう。
- 2018年12月5日 支払基金から厚労省へ誤った金額をメールで提出
- 2018年12月25日 厚労省から、金額のミスの指摘を受け、修正した金額をメールで提出(しかし、まだ間違っていた)
- 2018年12月27日 厚労省から保険団体へメールで金額を通知
- 2019年1月22日 支払基金がミスに気づく
- 2019年1月23日 厚労省に報告するが担当者レベルに留まる(2千円の間違いが、大きく影響するということを双方とも認識していなかった)
- 2019年3月5日 支払基金が厚労省に正しい数字に修正した報告書をメールで提出(ミスの重要度が分かっていないので出向いていない)
- 2019年3月6日 厚労省から支払基金へ修正理由の問い合わせ。ここで厚労省に出向いて説明
- 2019年3月7日 ミスの状況が、初めて支払基金理事長に届く
- 2019年3月8日 支払基金から厚労省幹部へ「影響が最大413億円」に及ぶと報告
- 2019年3月11日 厚労省が健康保険組合連合会(健保連)へ状況を報告
- 2019年4月4日 厚労省がミスの状況を正式発表
驚くべきことが2つあります。
支払基金の担当者がミスに気が付いたのは1月22日でしたが、それが同じ組織の理事長に届いたのは3月7日でした。
また、「誤りの恐れがある」と厚労省が支払基金から報告を受けたのは1月23日でしたが、健保連に伝わったのは3月11日でした。
つまり、支払基金でも厚労省でも、ミスの報告が1カ月以上も放置されていたのです。
報告書では、ミスが判明した後の処理が遅れたことについて、次の3点を挙げています。
- 事故発覚時、支払基金から厚生労働省へ連絡したが、その第一報が然るべきレベルおよび方法で報告されず、担当者の電話により行なわれたこと。また、担当者同士の意思の疎通が十分ではなく、指示内容の理解に齟齬があった
- 負担額が約2,000 円上がることによる保険料率への影響度を担当係長・担当者が十分に認識していなかったことおよび管理者のリスク管理意識が欠如していたことにより、上司や幹部に情報が上がらなかった
- 支払基金本部における事故報告の仕組み(悪い情報を速やかにあげる体制)が整備されていなかった
つまり、支払基金は自分が計算している数字が、どのように使われるかということを認識しておらず、ミスの処理を誤ったわけです。
また、厚労省側の担当者も、2千円というミスが数百億円の影響を招くということを認識していませんでした。
そのために、両方の組織とも、組織内のしかるべき責任者へ報告が上がることがなかったのです。
「どういう影響を及ぼすのか想像力を磨いてほしい」
今回の報告書の公開を受けて、根本匠(ねもと たくみ)厚労相は、記者会見で次のように述べました。
今回の事案は、極めて遺憾です。私から、担当部局と支払基金の双方に対して、厳しく注意するとともに、正確で丁寧な事務の遂行の徹底を厳しく指導いたしました。
今回の老健局と支払基金の対応は、これまでの方針を具体化するものであります。具体的には、「参考値」、「確定値」の決定に当たって、老健局長・支払基金理事長のハイレベル会合を開催して、決定プロセスに幹部がコミットすることで、慎重なチェックを担保すること、各課室・業務ラインごとに生じ得るリスクを事前に具体的に共有することで、幹部への速やかな報告を徹底することなどを実施いたします。
これらについて、しっかりと取り組ませます。今回の事案を通じて、厚生労働行政にとって大切なのは、国民の皆様に寄り添って施策を推進する視点だと改めて感じました。厚生労働省の職員一人ひとりがこの視点をしっかり持って日々の仕事に取り組んでもらいたいと思います。
さらに、次のように述べています。
要は今回の事案の私が国民の皆様に寄り添ってという視点が必要だというのは、この事案がどういう影響を及ぼすのかと、やはりそれぞれ業務を担当する担当者が厚生労働省は大きな予算を使っているわけだから、そして年金にしても医療にしても介護にしても国民の皆様に直接対応する政策をやっているので、そこの想像力、感性を磨いてもらいたいと私は思います。
厚労相も述べているように、たとえ、小さなミスであっても、それが健康保険の運営や、そこに所属している人のサイフに直接影響しているということを、常に意識して仕事をしてほしいものです。
もう一つ気になるのは、この報告書には「謝罪」という言葉が一つもないことです。
支払基金は、親方である厚労省には頭を下げたでしょうが、迷惑を掛けた健保連などの団体に詫びを入れたのでしょうか。他人事ながら心配になります。