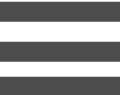毎年300人が死亡!? 年末年始の「餅」による事故に注意
[2021/12/10 00:00]

年末年始は、餅の事故の季節
12月に入って、スーパーのチラシに「餅(もち)」が載る季節になりました。
「餅」は、お正月らしい食材ですが、毎年、多くの人が死亡する事故の原因でもあります。
消費者庁では、今年も年末年始の「餅」の事故防止を呼びかけています。
1年に300人以上が死亡
消費者庁によれば、2018年からの2年間で、「餅」によって窒息した死者は661人に上りました。
1年間に300人以上が、餅をノドに詰まらせて死亡しているのです。
死亡事故の43%は「1月」に起きています。
次に多いのは「12月」なので、餅の事故は年末年始に集中していることが分かります。
特に、餅を食べる機会が多い、「三ヶ日」(1月1日~3日)や「元旦」(1月1日)には注意が必要です。
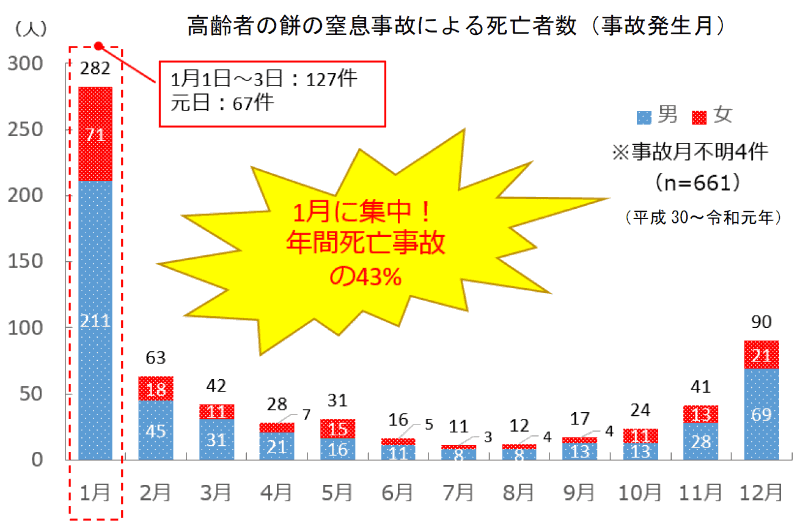
65歳からが危険な年齢
「餅」による事故は、高齢者に多いという特徴があります。
東京消防庁のデータを見ると、餅による事故で救急搬送された人の多くが、高齢者であることが分かります。
年代でいうと、65歳ぐらいから人数が増え、80代前半が一番多くなっています。
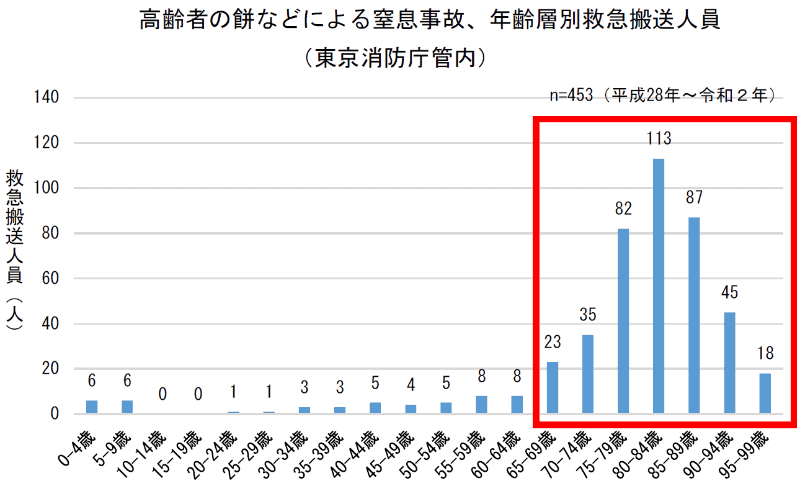
ひと手間かけて安全を確保
消費者庁では、餅による事故を防ぐためのポイントとして、次の5つを挙げています。
- 餅は、小さく切り、食べやすい大きさにしてください。
- お茶や汁物などを飲み、喉を潤してから食べましょう。
- 一口の量は無理なく食べられる量にしましょう。
- ゆっくりとよく噛んでから飲み込むようにしましょう。
- 高齢者が餅を食べる際は、周りの方も食事の様子に注意を払い、見守りましょう。
せっかくの年末年始を、悲しい思い出にしないためにも、餅を出す前にはひと手間かけ、食べるときには目を離さないようにしましょう。