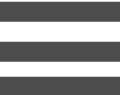国の研究機関が実証した、健康寿命を延ばすための10の行動

健康に生活できる年齢を示す「健康寿命」
健康寿命は、WHO(世界保健機構)が提唱した概念で、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されています。
日本人の健康寿命は、2016年の時点で、男性が「72.14歳」、女性が「74.79歳」でした。
「健康寿命」と「健康寿命」との差は、男性が8年、女性が12年余りもあります。
2つの寿命の差は、日常生活に制限のある「健康ではない期間」を意味しますから、できるだけ「健康寿命」を伸ばす工夫が必要となります。
しかし、健康寿命を伸ばすために方針は統一された形では提案されていませんでした。
今回、国立がん研究センターを始めとする、6つの国の機関が共同で「健康寿命延伸のための提言」をまとめました。
今回の提言の特徴は、それぞれの専門分野において、エビデンスがある、つまり有効性が確認されている方法をまとめていることです。
例えば、「喫煙をしない」「お酒を飲みすぎない」というのは、常識的な提案ですが、今回は、それぞれについて、健康寿命が伸びるという「有効性」が確認されています。
「健康寿命」を伸ばすための10の行動
さっそく、提言に示された10の行動を見ていきましょう。
1. 喫煙
- たばこは吸わない。
- 他人のたばこの煙を避ける。
2. 飲酒
- 節酒する。飲むなら節度のある飲酒を心がける。
- 飲まない人や飲めない人にお酒を強要しない。
3. 食事年齢に応じて、多すぎない、少なすぎない、偏りすぎないバランスのよい食事を心がける。
- 食塩の摂取は最小限(注1)に。
- 野菜、果物の摂取は適切に、食物繊維は多く摂取する。
- 大豆製品を多く摂取する。
- 魚を多く摂取する。
- 赤肉(注2)・加工肉などの多量摂取を控える。
- 甘味飲料(注3)は控えめに。
- 年齢に応じて脂質や乳製品、たんぱく質摂取を工夫する。
- 多様な食品の摂取を心がける。
(注1)男性7.5g/日未満、女性6.5g/日未満(厚生労働省日本人の食事摂取基準)
(注2)赤肉:牛・豚・羊の肉(鶏肉は含まない)
(注3)砂糖や人工甘味料が添加された飲料)
4. 体格
- やせすぎない、太りすぎない。
- ライフステージに応じた適正体重を維持する。
5. 身体活動
- 日頃から活発な身体活動を心がける。
例えば、「現状より1日10分でも多く体を動かすことから始める」としています。
6. 心理社会的要因
- 心理社会的ストレスを回避する。
- 社会関係を保つ。
- 睡眠時間を確保し睡眠の質を向上する。
7. 感染症
- 肝炎ウイルスやピロリ菌の感染検査を受ける。
- インフルエンザ、肺炎球菌を予防する。
8. 健診・検診の受診と口腔ケア
- 定期的に健診を・適切に検診を受診する。
- 口腔内を健康に保つ。
9. 成育歴・育児歴
- 出産後初期はなるべく母乳を与える。
- 妊娠糖尿病、妊娠高血圧症候群、巨大児出産の経験のある人は将来の疾病に注意する。
- 早産や低出生体重で生まれた人は将来の疾病に注意する。
S. 健康の社会的決定要因
- 社会経済的状況、地域の社会的・物理的環境、幼少期の成育環境に目を向ける。
例えば「個人の不健康の根本原因となっている社会的決定要因にも目を向け、社会として解決に取り組む」としています。
「普通に見えること」だが、継続することが課題
今回の提言の内容は、常識的と感じることが多く、特に「コレ」という目玉はありません。
しかし、逆に言えば、「健康に良い当たり前のこと」と感じていたことが、本当に健康に良いと証明されたことになります。
あとは、これらの「健康に良い当たり前のこと」をどれだけきちんと行なうかという問題になるでしょう。
実は、健康に良いと分かっていても、それを実行することが、一番むずかしいことかもしれません。