
第6回:碑文谷創氏に訊く「葬送」の現状と課題
葬儀は個々人の現実に即して組み立てよ
戦後高度経済成長が終焉し1991年のバブル景気崩壊、2008年のリーマン・ショックによる長期の経済不況で、葬送の世界も大きく変わったという認識は、葬送関係者の中では一致しています。しかし、その具体的な捉え方は、人によって異なります。
葬送の変化を俯瞰的、客観的に捉えることは難しく、また、その人の置かれた立場などによっても異なるからです。
そこで、葬送ジャーナリスト/葬送評論家として葬送の現状を鋭く見つめ、オピニオンリーダーとして長年に渡り活躍されている碑文谷創(ひもんや はじめ)氏に、葬送の現状をどのように捉え、葬送を行なう側の問題・課題点についてお話をうかがいました。
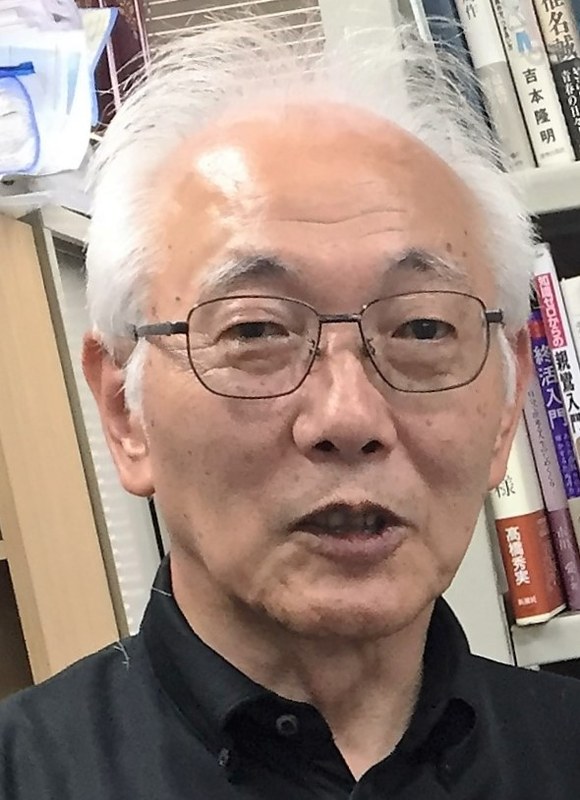
日本の祭祀を支えてきたのは「死者祭祀」
葬送の現状をどう見ていらっしゃるかお聞かせください。
先日、テレビを観ていたら、ある地方の人が「ご先祖様」という言葉を使っていました。「あ、ご先祖様という言葉が生きているんだな」と思いながら、ご先祖様の中身をよくよく聞いていると、「ご先祖様」とは亡くなった家族のことでした。自分の両親や祖父母が亡くなって「ご先祖様」になったと言っているのです。
それを聞いていて、亡くなった家族というのが、ご先祖様の原型に近いものではないかと私は思いました。
先祖とは、本来は、亡くなった人の数世代以前の血縁者全般を指した言葉ですが、現在は「数世代以前」ではなく、「数世代まで」と様変わりしてきているわけですね。しかし、碑文谷さんが、むしろ「数世代まで」が、先祖の原型に近いものではないかとおっしゃるのは、どういうことでしょうか。
民俗学者の柳田國男は、日本は農業社会なので、お父さんは自分の田畑を長男に譲り、次男には新しく田畑を開墾して生計が立つようにしてあげる。だから、次男の家の先祖はお父さんというとらえ方になると言っています。
要するに、現在の生活の基盤をつくってくれた人が、先祖というとらえ方です。
そういうとらえ方すると、現代社会は、多くの人には先祖がいない社会ということになります。
どういうことかと言うと、農業をしている人、商業をしている人、中小企業を営んでいる人などには先祖はいるかもしれないが、人口の圧倒的多くを占めるサラーリマンには先祖はいないことになるからです。
だから、先祖とは死んだ家族と捉える人が多くなってきているわけですね。そうしますと、「先祖祭祀(さいし)」とか「先祖供養」と言っていますが、その先祖が家族だとすると、言葉遣いと実態とは違うということになりますね。
そうなのです。文化人類学者や民俗学者などは「先祖祭祀」「先祖供養」と言っていますが、私は従来から、正しくは「死者祭祀」「死者供養」であると批判しています。
抽象的な先祖ではなく、その人や家族が具体的に知っている死者の祭祀、供養を行なっているのだから「死者祭祀」「死者供養」というのが正しいのです。
例えば、お盆というのは、自分の親とか亡くなったきょうだいなどが帰って来て、交流するという、死者との関係が非常に生々しい祭祀です。
あるいは、三十三回忌で弔い上げするのは、世代交代する時期と照応(しょうおう)しています。すなわち、その死者を直接に知った人がいなくなるから、弔い上げをするわけです。
ということは、死者との関係をきちんと取り続けていくのは、その死者と一緒に生きてきた人たちなのです。
一般の人は両親や祖父母といった近い死者を「ご先祖様」と言う。それを辞書的な「既に亡くなった数世代以前の血縁者全般のこと」という意味の「先祖」という言葉で表現して「先祖供養」と言うからおかしくなるのです。
「先祖供養」と言うと儀礼ぽくなりますが、もっと生々しい、人間的で、親しみのあるものなのです。
死者を捨てる家族も増えてきている
いまや、その死者祭祀すら危機にさらされていますね。
それは、家族分散があまりには激しいからです。あるいは、単身世帯が増えてきているからです。また、「私はひとり者」と公言していた人がいざ亡くなって調べると、家族や親族がいるというケースが多く見られます。
「親族関係」は明らかに弱体化しています。葬儀でも親族席は小さくなっています。都会に行くほどそうです。
叔父/叔母と甥/姪、あるいはいとこの関係が、一緒に住んだ、一緒に遊んだ、よく顔をつき合わせた関係でないケースが増加しているからです。きわめてプリミティブな人間関係がなければ「血縁」も意味をもたなくなります。
家族関係が密だった場合と、そうでなかった場合は、葬儀の時にもはっきり表れます。誰も何も言わなくても、柩のそばでジーッと故人に寄り添っている家族と、柩に近寄らずに遠巻きにする家族に分かれるのです。
昔は、家族は死者を大切にするものだということが当然とされていましたが、今は当然ではなくなり、死者を捨てる家族も増えてきています。
死者を捨てる家族というのは、どのようなケースですか。
殺人事件でも他人に殺されるより近親者に殺される方が統計的には多いのです。その人が嫌いだったので亡くなってくれてせいせいした、というようなケースは少なくありません。
昔からですが親子、兄弟(きょうだい)断絶は少なくありません。近年はそれに超高齢化という要素も加わっています。
小さくなった家族で身体や認知が不自由になった親の世話をすることで起こるストレス、負担などによって親が死ぬことの待望を招き、死亡して味わう解放感が喪失感を上回る事例も少なくありません。
昔も、親父のことが嫌いだったので葬式はやりたくないと思った人はいても、自宅で葬儀をしていたので、周囲の目があるから、いやいやながらでも葬式を行いました。
ところが今は葬儀会館(斎場)で葬儀をする時代、周囲の目はなくなり、規範が無くなったので、死者に対する意識がモロに出てきているのです。
引き取り手のない遺体は年間6~7万人
引き取り手のない遺体(遺骨)が増えてきているのも、その現れですね。
そうです。引き取り手のない遺体は、2010年にNHKが放映した「無縁社会」の時の調査では、年間3万2千人でした。厳密には、その中には身元不明の行旅死亡人が1千人含まれているので、引き取り手のない遺体は3万1千人です。
その後の推移を見ていると、現在は6~7万人位になっているのではないかと私は推定しています。
遺体を引き取らないのは、甥や姪が多くなっています。
2010年は3万1千人、現在は6~7万人ということは、ここ8年で倍になっているわけですね。
一方で、いやいやながらでも、遺体を引き取った人もいるわけです。それはつまるところ、相続問題に帰着します。
遺体の引き取り先が甥、姪であるということは、甥、姪が相続人であるからです。そして、甥、姪は、相続財産があると遺体を引き取り、相続財産がないと引き取らないのが現実だということです。
相続財産があるために、いやいやながらでも遺体を引き取る人は、引き取らない人と同じくらいいるでしょう。
そうすると、引き取る人と引き取らない人を合わせると、13万人くらいになります。13万人というと、年間死亡者数の約1割です。
それに「葬式無用」と考える人もいる。また、いま共同体がないので死者をどう取り扱っていいかわからない人が増えていますので、結果として「何もしない」=直葬という結果の人もいます。
直葬の全国平均は1割くらいと言われていますが、直葬1割というのは、不思議でもなんでもなく、そういう現実を反映しているだけの話です。
「孤独死」「孤立死」と呼ぶのは間違い
「孤立死」「孤独死」についても、良し悪しが論じられていますが、良し悪しの問題ではないということですね。
そうです。2015年の国勢調査で「1人世帯」が施設等世帯を除く一般世帯ではトップとなる34.5%を占め、約1,842万世帯です。
高齢者世帯でも単身世帯は多い。単身世帯が多ければ、誰にも看取られずに死ぬ「ひとり死」が増加するのは当然です。
私は、「孤立死」とか「孤独死」というのは、価値判断が入った言葉なので「単独死」と言っていました。
そうしたら、小谷みどりさん(第一生命経済研究所研究員)が「ひとり死」という言葉を使ったので、これは良い言葉だと思って、私も「ひとり死」と言っていますが、いまどき「ひとり死」を批判したら、単身世帯を否定するようなものです。
東京都監察医務院の東京23区で自宅において死後2日目以降に発見された死者は年間で3,657人です。私は全国では年間約2~3万人程度と推計しています。
例えば、人間が老いて病にかかりひとりで生活したら、よほど几帳面な人でない限り、綺麗に片づけられなくて部屋が乱れるというのは、当たり前のことです。
私は家族に「あなたひとりが生活していたらゴミの山」と常に言われています。その自覚があるから他人事ではない。
ひとり死の発見の55%は死後7日以内に発見されていますが、夏場であれば2日後でも腐敗の進行は早い。それ以外の季節でも7日あれば充分腐敗します。体液が漏れて、臭いのもあたりまえです。それが人間の死の現実です。
それなのに、その人の生前のことは何も知らない遺品整理業者などが、「これが社会から孤立している人の現実だ」などと言ってよい権利がどこにあるのか。
しかも、亡くなった後の一番大変な遺体処理を行なっているのは警察や葬祭業者なのであって、その後のことを、お金をもらって行なっているだけの業者が、偉そうなことを言ってはいけません。
中には、同じような内容の「孤独死」「孤立死」の本を何冊も出している業者もいますよね。
本を出している人がすべておかしいわけではありませんが、便乗している人もいますね。
警察にしろ、葬祭業者にしろ、いろいろな仕事をしても、それが「特殊な仕事」とはけっして言いませんし、死者に対する礼意が要求されています。その内容を無責任に口外したりはしません。それは、自分の仕事としてやっているからです。それがプロというものです。
「特殊清掃」なんて言葉がありますか。仕事の難度が高い仕事は世の中にはたくさんあります。それをいちいち「特殊」とは言わないでしょう。ましてやプロなのですから。自負もあるでしょうが、死者を貶める言葉と私には聞こえます。
遺品整理業者も、さまざまな困難を抱えていることはわかりますが、それを何とかするのは仕事を受けた業者の責任です。
それなのに、あたかも死んだ人間に責任があるかのように言うのは、そもそもおこがましいのです。人間の尊厳を考えない一部の業者の言動には、怒りを覚えます。
立ち合う人がいない葬儀は葬祭業者が弔うべき
直葬の話に戻りますが、直葬や福祉葬などの立ち合う人が少なかったり、いなかったりする葬儀に対する葬祭業者の姿勢については、どのように感じていらっしゃいますか。
誰も弔う人がいないので可哀そうとか、葬儀を行なうのに困るという葬祭業者がいますが、私は、「立ち合うのが担当者であるあなた一人であったとしても、あなたには弔う責任があるし、それが葬祭業者の仕事、倫理というものではないか」と言っています。
どのような人間でも尊厳があり、弔われる権利があります。だから、葬祭業の担当者が弔うことによって、死者の尊厳が確保されるのです。
葬祭業者すべてが、それぐらいの覚悟を当たり前のこととしてもたないと、人間の尊厳は保たれません。
どのような死に方をしても、家族が分らない、引き取り手がいない場合は、自治体で葬儀を行なうのは、死者の最低限の人権を守るためです。
だから、今の時代は、福祉葬や単身者などで立ち合う人が誰もいない葬儀こそ、きちんと行なうべきなのです。
そういう意識が葬祭業者や宗教者の根底にあってこそ、すべての葬儀にきちん向き合っていけると思うのです。
「直葬はあまり儲からないから嫌だ」とか、「立ち合う人がいない葬儀は可哀想な仕事だ」などと言っているのは、プロではないということですね。
そうです。そう思うような葬祭業者や僧侶は、きつい言い方をすれば「やめろ」と思います。
昔、コンサルタントと名乗る人が、話を聞きたいと私の事務所にやってきて、「葬儀というのは、遺体を取り扱わなければ非常に良い仕事ですね」と言った時、私は「お前、帰れ」と怒鳴り追い出したことがありました。
遺体を取り扱わない葬祭業者なんてあり得ませんよね。
そうなのですが、でも私は、葬祭業にはそれに近い認識が蔓延していると見ています。
例えば、通夜や葬儀・告別式という儀式だけが重要だと思っている葬祭業者が少なくないのです。
しかし、葬儀というのは、遺体の引き取りから始まって、火葬して終わるまで、その後のフォローもあるけれども、少なくともそこまでが葬儀で、それをきちんとやり抜くことが葬祭業者の仕事なのです。
死は個別であり、葬儀も個別に対応しなければいけない
葬儀と告別式に関して言いますと、いま、葬儀のかたちを、「一般葬」、「家族葬」、「一日葬」、「直葬」とに分けて、生活者に提案しているのが一般的です。これについては、どう思われていますか。
腹立たしいことから言うと、「一般葬」という言葉です。これは、家族葬という言葉が出てきたことによって使い始めた言葉です。
脳死という概念が出てきたことによって、心臓死という言葉がでてきたことに似ていますが、一般葬なんてあり得ません。
なぜなら、それぞれの死者、それぞれの家族がいて、それぞれの想いや感情があって葬儀があるのだから、それぞれに対応するのが葬儀だからです。
死者や家族の状況はそれぞれ違い、今の時代はなおさら違ってきているわけだから、それぞれ個別に対応しないと、葬儀を行なうことは不可能なのです。

また、本当に関係のある人たちだけで葬儀を行なうのは当たり前だろうと思います。
しかし、現実には遺族が故人と関係のある人すべてを知るわけではないし、むしろ把握していない方が多い。
だから、遺族が知る範囲だけに限定すると故人と深く関係した人が漏れるおそれがあります。閉じすぎた故の弊害も少なくありません。
死者や家族それぞれに個別の葬儀を行なうためには、どういうことが重要ですか。
厚生労働省認定の「葬祭ディレクター技能審査制度」というのがあります。これは、葬祭業界に働く人にとって必要な知識や技能のレベルを審査し、認定する制度です。
私は、発足当初から2016年まで約20年関わってきました。
試験の一つに接遇試験があります。最初に、亡くなった人の想いや、家族の死者に対する想いを聴くことから始めなさい、そうしないと減点しますよとしています。
要するに、葬儀の打ち合わせでは「どのような祭壇にしますか」といったことから始めるのではなく、死者や家族の想いや、抱えている問題点などを把握してから葬儀を組み立て、提供するのがプロというものだろうということです。
一言(ひとこと)でいいますと、「葬儀は現実に即して組み立てよ」ということですね。
そうです。葬儀はリアル、現場に即応したものでなければ、もはや通用しません。
東京・世田谷の葬儀社の社長3人と昔葬儀現場でアルバイト経験のある役者さんの4人がYouTubeで配信している「びきまえ(友引前)」という番組があります。
彼らが面白いのは、現場のリアルさを何よりも大切にしていることです。だからあの放送は多くの人が聴いているのだと思います。
私は、彼らのように葬儀のリアルにきちんと立って発言し、行動するたちが増えていくことが、葬儀業界に一番必要なことだと思います。
本日は、葬儀の現実を考える上で有益なお話をありがとうございました。
【碑文谷創氏のプロフィール】
葬送ジャーナリスト。評論家(死、葬送、宗教)。
1946年生まれ。東北出身(岩手・一関、宮城・仙台)。東京神学大学大学院修士課程中退。
出版社に勤務し、44歳で独立、葬送文化専門雑誌『SOGI』編集長(1990~2016)。
経産省「ライフエンディング・ステージ」研究会委員(2010~2011)、葬祭ディレクター技能審査企画委員(1995~2016))、IFSA(一般社団法人日本遺体衛生保全協会)顧問(1993~)等を歴任。
本邦初で唯一の「死と葬送」に関する総合歴史年表(「人の死・葬送を歴史のコンテキストで読む」)をまとめるなど葬送分野の歴史・記録の編著が多い。『全葬連50年史』『葬祭ディレクター技能審査20年史』『IFSAの20年』『3.11東日本大震災 弔鐘―宮城県葬祭業協同組合の活動記録』等。
現在、死、葬送、宗教に関する評論・講演活動を展開。
著書は『「お葬式」はなぜするの?』、『死に方を忘れた日本人』『葬儀概論』(現在4訂)ほか多数。
記事に関連するWebサイト
塚本 優(つかもと まさる)
葬送ジャーナリスト。1975年早稲田大学法学部卒業。時事通信社などを経て2007年、葬祭(葬儀、お墓、寺院など)を事業領域とした鎌倉新書に入社。葬祭事業者向け月刊誌の編集長を務める。また、新規事業開発室長として、介護、相続、葬儀など高齢者が直面する諸課題について、各種事業者や専門家との連携などを通じてトータルで解決していく終活団体を立ち上げる。2013年、フリーの葬送ジャーナリストとして独立。葬祭・終活・シニア関連などの専門情報紙を中心に寄稿し、活躍している。

