
第29回:デジタル世界は供養に向いているのか――瓜生大輔さんと考える
インターネットなどのデジタル技術はとても便利ですが、伝統的な儀式とは掛け合わせが難しい側面があります。
故人の写真や言葉を無劣化で残せるデジタル世界と、従来の葬送や供養文化はどう関係するのがよいのでしょうか。「デジタル供養」に関して研究する、東京大学の瓜生大輔(うりう だいすけ)博士に尋ねました。

動的な遺影「Fenestra」でデジタル供養を模索
瓜生大輔さんはメディアデザインを主とする研究者で、2014年に祭壇型フォトフレーム「Fenestra(フェネストラ)」の論文(PDF)により博士号を取得しています。
自作のFenestraを年代の異なる複数の人に一週間使ってもらい、デジタルの形見がもたらす供養経験を調べる内容でした。
Fenestraは、手前にあるキャンドルホルダーに火を灯したり円鏡を見つめたりすると写真が浮かび上がる仕組みで、炎が揺らぐと次の写真に自動で切り替わります。
特定の宗教儀礼の所作に依らず、デジタル機器らしい操作を必要とせず、遺影や祭壇を前にした際の自然な振る舞いだけで使えることが意識されています。

50代の女性は試用後にこう語っています。「最初、故人がこういう風に出てくるのは、どうかな……と思ったけど、だんだん印象が変わってきました。あまり(亡くなった人の写真は)見たくない時あるじゃないですか。でも、朝とか、チラチラ出てくると楽しかった。ほんとに『ああ、居るんだ』みたいに感じる」(論文からの抜粋)
遺影とは違い、動的な存在として故人の思い出と対面できたといった感想は他の試用者からも聞かれました。また、好きな写真を追加できること、動画も表示できることに喜ぶ声もありました。このあたりはデジタルの形見ならではの特長といえるかもしれません。
Fenestra自体はあくまで研究用のツールなので現在のところ商品化などの計画はありませんが、研究の根本にある「デジタル供養」については瓜生さんの主要な研究テーマであり続けています。
デジタルが向いているのは「供養」より「追憶」か
私自身の取材経験を振り返ると、このデジタルと供養の掛け合わせは簡単ではないと感じます。
数年前、インターネットで葬儀会場を中継してヴァーチャル参列できるサービスを開発したベンチャーがありましたが、普及したという話は聞きません。
スマホやパソコンでログインしていつでもヴァーチャル線香などをあげられるオンライン上の個人墓(サイバーセメタリー)サービスは10年以上前から複数ありますが、状況は似たり寄ったりです。
伝統的な供養や弔いの場に闇雲に導入すると、強烈な異質感が儀式本来の厳粛さを損ねてしまう。そうした作用が最新のデジタル技術にはあるようです。
しかし一方で、葬儀の遺影写真にデジタルフォトフレームが広く使われていたり、故人のブログに何年経ってもコメントがつけられて追悼の場として機能していたりする事実もあります。
どういった塩梅でデジタルを組み込んでいけばいいのか。瓜生さんは、イマジネーションと追憶を分けて考えることが大切だと言います。
「たとえばお葬式に飾られる遺影は、元の写真をトリミングするのではなく、顔写真だけ切り抜いて背景を抽象的にしていることが多いですよね。あれは弔問客の集中力を高めるためだと思うんですよ。葬儀は極限までイマジネーションを高めて亡くなった人に想いを伝える場じゃないですか。そこに集中したいとき、『あ、たぶん社員旅行のときのだ』みたいな具体性は邪魔になってしまう。
故人を想う、心の中で語りかける、というのと、故人との思い出を具体的に思い出すというのは実は別の行為で、デジタルの形見はどちらかといえば後者に向いていると思います。抽象よりも具体。だから、想像力を高めるために極限まで抽象化する儀式には、そのままの状態では“ずれ”が生じるのかもしれません」
デジタル環境に残された膨大な写真は、その人の姿形だけでなく交友関係や振る舞い方などをはっきりと伝えます。これまた膨大な投稿やチャットはその人なりの語彙や出来事、考え方などを相当具体的に浮かび上がらせます。
それらの特性をそのまま生かすとなると、余計なディテールを捨象して故人を想う宗教儀式とは確かに“ずれ”が生じてしまいそうです。
それよりも向いているのは追憶に特化したシチュエーションといえるでしょう。
葬送関連の儀式で重要な「供養」とは故人の冥福を祈るための行為で、どこかにいる故人に対して向き合う行為といえます。
一方の「追憶」は過去の思い出を掘り起こす行為です。過去の具体的な断片は、追憶の強力な味方になるはずです。
「お葬式が終わった食事の席でデジカメ写真のスライドショーを流したり、自宅などのプライベートな空間で故人に思いを馳せたりするときに、デジタルの形見は強みを発揮するんじゃないかと思います」
デジタル化ではなく、デジタルならではの新しい何か
もちろん、デジタル自体が葬送と相性が悪いというわけではありません。デジタル技術は連絡ツールや葬儀等のバックグラウンドですでに広く使われています。ただ、完成された儀式の空間に持ち込んだり価値観を拝借したりするのは、互いの性質を見た上で慎重になったほうがいいでしょう。
瓜生さんは「デジタル化じゃなくて、デジタルだからできる新しい向き合い方を考えるほうがいいのかもしれません」と提案します。
実際、先行例もあります。
前述のとおり、現実のお墓を“デジタル化"したサイバーセメタリーはあまり普及していないのが現状ですが、1996年から運用している米国の追悼専用サイト「Virtual Memorials」は3万件以上の登録がありますし、SNS等から収集した故人の情報から作ったアバターとコミュニケーションがとれる「Eterni.me」は2014年スタートですでに登録が4万件を越えているといいます。
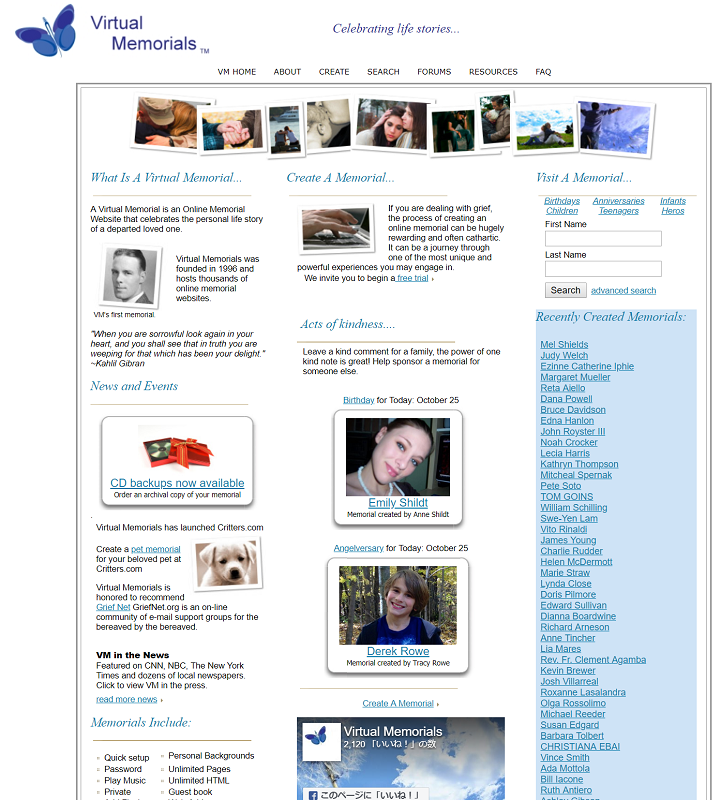
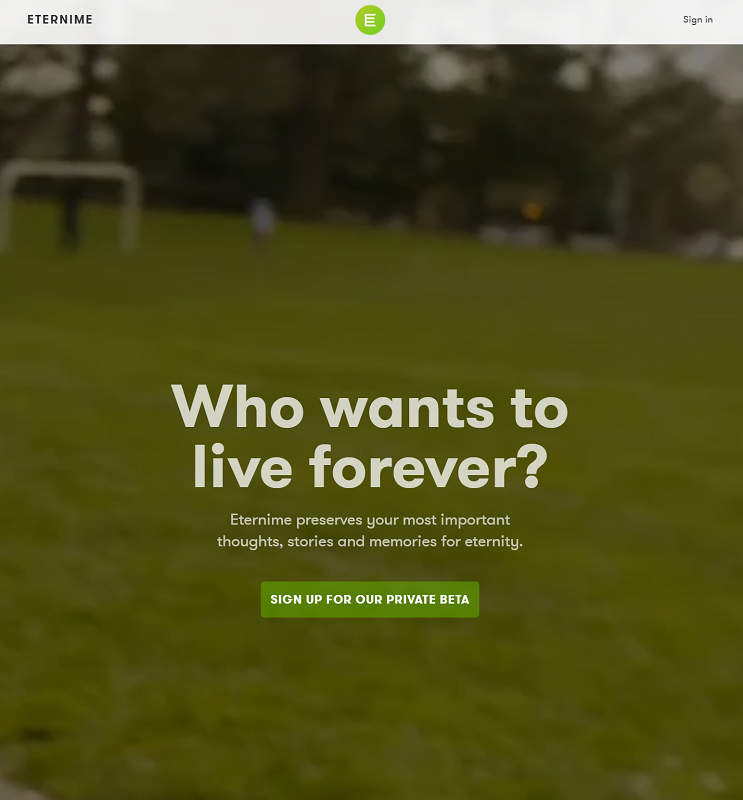
以上を踏まえると、「デジタル供養」というテーマを突き詰めていくと、本義である供養性を追求する方向よりも、儀式性に頼らない「デジタル追憶」あるいは「デジタル追悼」といった方向に進むように思います。
瓜生さんが探り続ける「デジタル供養」は、そうした追憶や追悼を内包した広義の意味合いも含むでしょう。そのうえで狭義の供養の可能性も大切にしています。
「オンラインでしかつながりのない人との別れをどうするかと考えたとき、対面した人と同じように何かしてあげたくなるのが人情だと思います。そこで何かしらの(故人に働きかける行為としての)供養がオンラインというデジタル環境で実現できないかというところは気になっています」
仏式の葬儀はかつては当時の最新技術と知見を生かした儀式でした。遺影が飾られるようになったのも日露戦争時代が始まりと言われ、100年程度の歴史しかありません。
伝統的とみられる文化や風習も絶えず変化しているので、いずれはデジタルとの融合を果たすかもしれません。それがどんな形になるのか、今後も追っていきたいと思います。
連載内の関連記事
古田雄介(ふるた ゆうすけ)
1977年生まれのフリー記者。建設業界と葬祭業界を経て、2002年から現職。インターネットと人の死の向き合い方を考えるライフワークを続けている。書き手が亡くなった100件以上のサイトを追った書籍『故人サイト』(社会評論社)を2015年12月に刊行。2016年8月以降、デジタル遺品研究会ルクシー(http://www.lxxe.jp/)の理事を務めている。2017年8月にはデジタル遺品解決のための実用本『ここが知りたい! デジタル遺品』(技術評論社)を刊行する。

